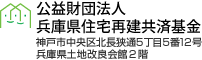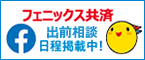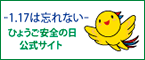- Q1 何故、この様な制度を設けたの?
- Q2 どんな共済制度があるの?
- Q3 加入できる住宅は?家財は何か制限があるの?
- Q4 1つの住宅に複数口加入できるの?
- Q5 賃貸住宅のオーナーは何に加入できるの?
- Q6 相続した住宅に住んでいるが、まだ名義を書き換えていない場合は?
- Q7 加入申込書はどこにいけばあるの?
- Q8 加入はいつからできるの?
- Q9 共済負担金は?
- Q10 共済負担金の支払い方法は?
- Q11 共済給付金はどのような場合に支払われるの?
- Q12 火事では給付されないの?
- Q13 被害は誰がどのように認定するの?
- Q14 いつまでに給付申請したらいいの?
- Q15 地震保険やJA共済とはどう違うの?
- Q16 地震保険料控除は受けられるの?
- Q17 毎年の共済負担金はどうなっているの?
- Q18 フェニックス共済に還付金はあるの?
Q1 何故、この様な制度を設けたの?
答え
平成7年1月の阪神・淡路大震災では、多くの被災者が住宅の再建に多くの苦労をされました。
このため、自然災害の被害に対して住宅所有者相互の助け合いの仕組みとして平成17年9月に創設されたのが「住宅再建共済」です。
その後、平成21年8月の台風9号災害を契機として、家財を対象とし、賃貸住宅入居者も加入できる「家財再建共済」も創設され、県民相互の助け合いの仕組みとなっています。
さらに、平成25年4月の淡路島を震源とする地震では、被害全体に対する準半壊の被害の割合が大きかったことから、平成26年8月1日(金)から住宅再建共済及びマンション共用部分再建共済に準半壊特約をスタートしました。給付対象が広がり、より確かな安心を得ることができる制度となりました。
Q2 どんな共済制度があるの?
答え
3つの共済制度があります。
- 住宅を所有している方が加入できる「住宅再建共済制度」(平成17年9月)
- 家財を対象に住宅居住者が加入できる「家財再建共済制度」(平成22年8月)
- マンションの共用部分を対象に管理組合が加入できる「マンション共用部分再建共済制度」(平成19年10月)
いずれの制度も兵庫県の条例に基づき運営されている「安心」、「安全」の制度ですので、他の共済制度や損害保険に加えて加入していただけます。
※平成26年8月からは「住宅再建共済」「マンション共用部分再建共済」に準半壊特約制度がスタートしました。
Q3 加入できる住宅は?家財は何か制限があるの?
答え
住宅再建共済に加入できる住宅は、兵庫県の区域内に存する住宅で、一定の要件を満たすものです。例えば、持ち家の戸建住宅・分譲マンション、借家・賃貸マンション・社宅等、別荘・セカンドハウス、店舗併用住宅の住宅部分などです。 なお、家財再建共済は、住宅再建共済の加入要件を満たした住宅の中にある家財を対象としていました。
Q4 1つの住宅に複数口加入できるの?
答え
県民相互の助け合いの仕組みとして、少しでも多くの方に加入していただけるよう、1戸の住宅に1つだけ加入いただけます。
Q5 賃貸住宅のオーナーは何に加入できるの?
答え
賃貸住宅の所有者として住宅再建共済に加入できます。家財再建共済は、居住者(入居者)に加入資格がありますので、賃貸住宅のオーナーは加入できません。
また、住宅再建共済に加入する時は、自然災害で被災して再建する時のことを考えていただき、1戸~賃貸住宅の全戸数の間で加入する戸数を決めていただけます。
Q6 相続した住宅に住んでいるが、まだ名義を書き換えていない場合は?
答え
実際にお住まいであったり、毎年の固定資産税を負担しているなど実質的な所有者であれば加入できます。加入時には特別な書類は必要ありませんが、共済給付金の申請時に相続関係を示す書類等を添付して給付申請していただくことになります。
Q7 加入申込書はどこにいけばあるの?
答え
加入申込書は、県(県民局、県民センター)・市町のロビーや担当課、兵庫県内の郵便局、コープこうべなどに置いてもらっています。また、基金事務局にお電話078-371-1000いただければ郵送いたします。
Q8 加入はいつからできるの?
答え
加入申込書が基金事務局に届いた日です。兵庫県内835の郵便局(簡易局を除く)や、県民局・基金事務局に加入申込書を持参された場合は、その日から加入できます。
なお、インターネットからも申込できますが、加入日は翌日(午前0時から)となります。
Q9 共済負担金は?
答え
フェニックス共済は年度単位での加入ですので、共済負担金は年額で設定しています。 ただし、加入初年度は、加入日の属する月から次の3月までの月数で計算します。
(本体制度)
| 住宅再建共済 | 家財再建共済 | マンション共用部分 再建共済 |
|
|---|---|---|---|
| 年額 | 5,000円/戸 |
1,500円/戸 | 2,400円/戸×マンションの住宅部分の戸数(全住宅戸数、店舗は含みません) |
| 加入初年度の場合 | 月額500円 ×次の3月までの月数 (上限5,000円) |
月額150円 ×次の3月までの月数 (上限1,500円) ただし、住宅再建共済と家財再建共済の両方に加入する場合は、家財再建共済を最高500円割引します(年額1,000円/戸、月額100円)。 |
月額200円 ×次の3月までの月数 ×マンションの住宅部分の戸数(住宅戸数、店舗は含みません) |
(準半壊特約)
| 住宅再建共済 | マンション共用部分 再建共済 |
|
|---|---|---|
| 年額 | 500円/戸 |
250円/戸 ×マンションの住宅部分の戸数 (全住宅戸数、店舗は含みません) |
| 加入初年度の場合 | 月額50円×次の3月までの月数 (上限500円) |
月額25円 ×次の3月までの月数 ×マンションの住宅部分の戸数(住宅戸数、店舗は含みません) |
Q10 共済負担金の支払い方法は?
答え
現金を取り扱うことによる事故を防ぐために、口座振替(ゆうちょ銀行、その他の金融機関)とクレジットカードの利用としています。なお、インターネットでの加入はカード支払のみとなります。
口座振替
新規加入時は加入日の翌月の27日に指定の口座から振り替えます。継続分は毎年3月27日口座振替します。
クレジットカード
新規加入時は約2週間後にカード会社と決済しています。
具体的には、加入者とカード会社との間で設定した請求日に請求されます。
Q11 共済給付金はどのような場合に支払われるの?
答え
台風や地震などの自然災害で被害を受け、住宅や家財の再建・購入・補修等をした場合です。
住宅再建共済
(本体制度)
| 給付金 | 給付対象 | 給付金額 |
|---|---|---|
| 再建等給付金 | 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊で建築・購入 | 600万円 |
| 補修給付金 | 全壊で補修 | 200万円 |
| 大規模半壊で補修 | 100万円 |
|
| 中規模半壊・半壊で補修 | 50万円 |
|
| 居住確保給付金 | 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊で建築・購入・補修をせずに賃貸住宅に入居した場合等 | 10万円 |
(準半壊特約)
| 給付金 | 給付対象 | 給付金額 |
|---|---|---|
| 補修等給付金 | 建築または購入した場合 | 25万円 |
| 補修した場合 | 25万円 |
|
| 居住確保給付金 | 建築・購入・補修をせずに 賃貸住宅に入居した場合 |
10万円 |
(注)1 県外で建築・購入の場合、給付額は300万円となります。
(注)2 賃貸住宅等については、次の制約があります。
(1)再建等給付金は、兵庫県外での建築・購入は給付対象となりません。
(2)居住確保給付金は、給付対象となりません。
家財再建共済
| 給付金 | 給付対象 | 給付金額 |
|---|---|---|
| 家財再建共済給付金 | 住宅が全壊で家財を補修・購入 | 50万円 |
| 住宅が大規模半壊で家財を補修・購入 | 35万円 |
|
| 住宅が中規模半壊・半壊で家財を補修・購入 | 25万円 |
|
| 住宅が床上浸水で家財を補修・購入 | 15万円 |
マンション共用部分再建共済
(本体制度)
| 給付金 | 給付対象 | 給付金額 |
|---|---|---|
| 再建等給付金 | 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊で建築 | 300万円×新たなマンションの住宅部分の戸数(加入時の住宅部分の戸数が上限) |
| 補修給付金 | 全壊で補修 | 100万円×住宅部分の戸数 |
| 大規模半壊で補修 | 50万円×住宅部分の戸数 | |
| 中規模半壊・半壊で補修 | 25万円×住宅部分の戸数 |
(準半壊特約)
| 給付金 | 給付対象 | 給付金額 |
|---|---|---|
| 補修等給付金 | 建築した場合 | 12万5千円 ×新築マンションの住戸数 (加入時の住戸数を上限) |
| 補修した場合 | 12万5千円×加入時の住戸数 |
(注) 県外で建築の場合、給付額は300万円となります。
Q12 火事では給付されないの?
答え
失火等人為的な原因による火事では、給付の対象となりません。
自然災害による被災を対象としますので、地震を原因とした火災(延焼を含みます)は、給付の対象となります。
Q13 被害は誰がどのように認定するの?
答え
加入した住宅(家財が存する住宅)が所在する市町がり災証明書を発行します。り災証明書は、内閣府が定める「住家の被害認定」という基準に基づいて判定されます。
次の表のどちらか高い方で判定します。
| 区分 | 損壊部分の床面積割合 | 経済的損害の割合 |
|---|---|---|
| 全壊 | 70%以上 | 50%以上 |
| 大規模半壊 | 50%以上70%未満 | 40%以上50%未満 |
| 中規模半壊 | 30%以上50%未満 | 30%以上40%未満 |
| 半壊 | 20%以上30%未満 | 20%以上30%未満 |
| 準半壊 | 10%以上20%未満 | 10%以上20%未満 |
なお、家財再建共済の給付対象となる床上浸水は「住宅の床より上に浸水したもの又は全壊、大規模半壊、中規模半壊若しくは半壊には該当しないが、土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないもの」という状態です。床上浸水でも浸水高が高く壁等の被害が大きい場合は、半壊以上の被害認定になることがあります。
Q14 いつまでに給付申請したらいいの?
答え
自然災害が発生してから5年以内です。
Q15 地震保険やJA共済とはどう違うの?
答え
住宅などの価値に着目して、その損害を補てんする地震保険や他共済と違い、フェニックス共済は自然災害で被害を受けただけでは給付されず、補修や建替え等の住宅・家財の再建が必要となります。
また、地震保険等は火災保険の保険金額の50%までしか入れませんので、住宅等の再建を考えた場合、自ずと自助努力が必要となります。フェニックス共済は、この部分に県民相互の助け合いとして給付するものですし、住宅の築年数等に左右されず定額で給付されるのが特徴です。
このように、フェニックス共済は、地震保険等と違うものとして県が条例で定めたものですので、地震保険等とは別に加入することができます。
Q16 地震保険料控除は受けられるの?
答え
地震を対象とする制度ではありますが、地震保険料控除の対象となっておりません。
このため、地震保険料控除の証明書等はお送りしておりません。
Q17 毎年の共済負担金はどうなっているの?
答え
共済負担金は、その殆どを将来の自然災害の被害により給付する時に備えて、安全・確実な方法で積み立てをしています。
Q18 フェニックス共済に還付金はあるの?
答え
フェニックス共済は、県民相互の助け合いの仕組みとして、共済負担金の殆どを積み立てにまわし、県内の他の地域で自然災害が発生した場合に給付するという、いわば義援金の前払いの仕組みであり、還付金はありません。